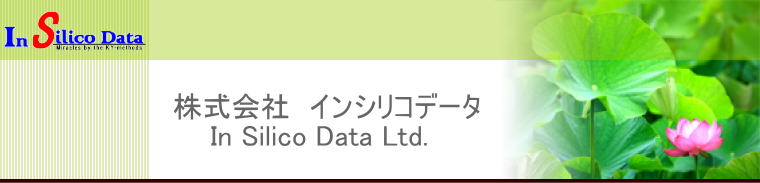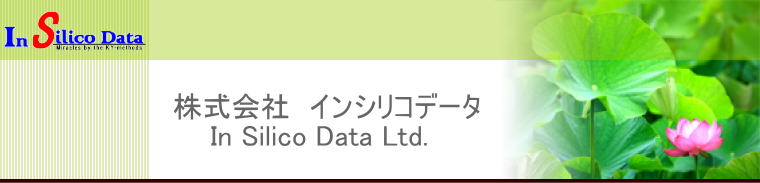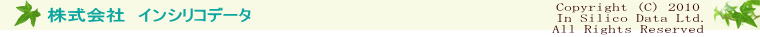|
|
 化合物と安全性(毒性):QSARとQSTR 化合物と安全性(毒性):QSARとQSTR |

現在、化合物に関する安全性(毒性)の問題が化合物開発時に解決すべき重要な問題となりつつあります。「安全性」と「毒性」は相互に対立する言葉ですが、化合物開発という観点では同義語と考えられます。安全性(毒性)は創薬分野では生体毒性が主体となり薬事法等の規制のクリアが必要であり、この他にも副作用の無い薬物の設計が必須となります。一方で、近年急速に関心が高まっている「環境」との関係で、一般/機能性化合物を研究対象とする場合は生態毒性を考慮することが必要で、この場合もREACH、化審法やTSCA、他等のクリアが必要となります。
安全性(毒性)研究分野ではQSAR(定量的構造-活性相関)が安全性(毒性)評価に重要な技術とされていますが、活性と毒性は内容も本質も大きく異なり、毒性を対象とした研究はQSTR(定量的構造-毒性相関)となります。
薬理活性の特殊なものが毒性であるとして毒性を扱う場合もありますが、現時点で展開されているQSARは、その基本原理が薬理活性研究に特化しております。このため、薬理活性を扱うのと同じ考えで毒性をQSARで扱う場合は、その適用限界や基本原理等の差異を充分ご理解の上で注意深く適用することが必要です。 |

 定量的構造-活性相関(QSAR)と構造-毒性相関(QSTR) 定量的構造-活性相関(QSAR)と構造-毒性相関(QSTR) |
 薬理活性と毒性の違い 薬理活性と毒性の違い
|
![]() |
 定量的構造-活性相関と定性的構造- 定量的構造-活性相関と定性的構造-
活性相関
|
![]() |
 構造-活性相関(QSAR)と構造-毒性相関(QSTR)の違い 構造-活性相関(QSAR)と構造-毒性相関(QSTR)の違い
|
![]() |
 構造-活性相関(QSAR)と構造-毒性相関(QSTR)適用限界 構造-活性相関(QSAR)と構造-毒性相関(QSTR)適用限界
|
![]() |
 毒性評価にQSARを適用する場合の典型的なアプローチ 毒性評価にQSARを適用する場合の典型的なアプローチ
|
![]() |
 毒性評価に化学多変量解析/パターン認識(ケモメトリックス)を適用する場合の典型例 毒性評価に化学多変量解析/パターン認識(ケモメトリックス)を適用する場合の典型例
|
![]() |
 生体毒性と生態毒性 生体毒性と生態毒性 |
 生体毒性と生態毒性の違い 生体毒性と生態毒性の違い
|
![]() |
 毒性項目(エンドポイント)の種類 毒性項目(エンドポイント)の種類
|
![]() |
 化合物規制と内容 化合物規制と内容 |
 代表的な化合物規制 代表的な化合物規制
EU:REACH、日本:化審法、USA:TSCA、その他
|
![]() |
 検査項目 検査項目
|
![]() |
 毒性予測に対するKY法およびテーラーメードモデリングの有効性 毒性予測に対するKY法およびテーラーメードモデリングの有効性 |
 KY法は何故毒性予測に適しているのか? KY法は何故毒性予測に適しているのか?
|
![]() |
 テーラーメードモデリングは何故予測精度を重視した毒性予測に適しているのか? テーラーメードモデリングは何故予測精度を重視した毒性予測に適しているのか?
|
![]() |
|
|